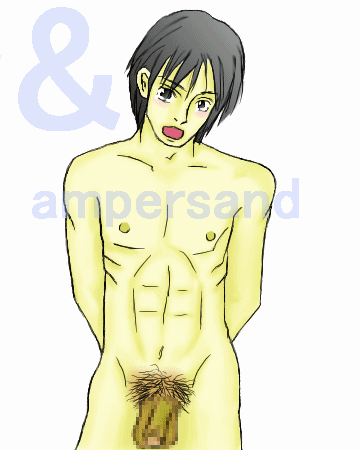
vanilla
2005.01.15
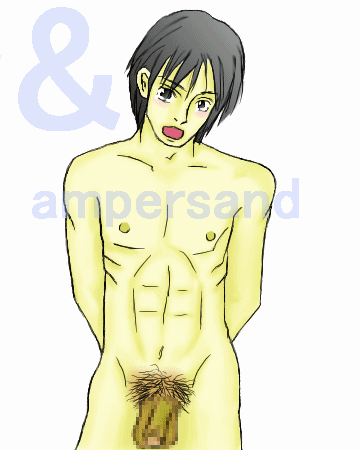
|
「今日誰もいないから泊まりに来いよ。」 恋人である祥司の誘いに裏を感じてミツルは曖昧に笑った。 入学当初どちらかと言うと優等生タイプだったミツルは、不良っぽい風貌の祥司とは何も接点が無いような気がしていたが、どういう訳か祥司に気に入られていた。 始めは鬱陶しく思っていたが、見た目と違って毎日熱心に口説いてくる祥司の健気さに心が動かされるまで、それほど時間はかからなかった。 結果、強引な祥司に押されて付き合う事になったが、祥司の望むような身体の関係はこの三年間でまだ無い。 ミツルは口と手だけでも充分だと思うが、祥司はそれだけでは満足出来無いらしい。 なんとなく嫌な予感はしたが、一緒にいたい気持もあってミツルは複雑な気持で祥司の誘いに頷いた。 「おい、何だよこれ…。」 夕飯の後、テレビを見ていてウトウトしていたのがいけなかったのかもしれない。 裸にされているのはまだマシとして、両手を後ろで縛られているのが納得がいかない。 「いや、お前暴れるだろ?」 「はぁ? ふざけるなよ、暴れるような事しなきゃいいだろっ。」 「ふざけてるのはどっちだよ。」 付き合い始めてすぐの頃から祥司はセックスの度に一つになりたがった。 しかし小心者のミツルは祥司の欲望を受け入れる事が出来ずに、それらしい言い訳をしながら今日まで誤魔化し続けている。 強引に迫る時もあったが、いざという時にミツルが泣き出してしまい最終的には未遂に終わって、そっちの世界ではバニラと呼ばれる口と手を使ったセックスで若さで持て余した性欲を満たしていた。 「まだ無理だって…。」 「三年間も待ったんだぞ、もういいだろ。」 ずっと我慢してくれている事に感謝はしていたし、待たせ過ぎている事に不安を感じる事もあったが、一度してしまったら何かが変わってしまうようで祥司を受け入れる事に踏み切れ無かった。 「今まで通りじゃ駄目なのかな……。」 言訳を遮るように祥司が唇を重ねると、敏感な部分を指でくすぐりながら徐々に反応していくミツルの身体を楽しむ。 「ちゃんと剥いとけっていつも言ってるだろ。」 股間に伸びた冷たい指に腰を引くともう一方の手が力強く肩を掴んで引き寄せた。 祥司はいつもミツルのコンプレックスを意地悪く突ついて黙らせようとする。 「仕方無いだろ……まだ高校生なんだから。」 「俺だって高校生だぜ。」 祥司は大きく上に持ち上がった立派なモノをミツルに向かって自慢気に突き出した。 日本人の7割は…とお決まりの台詞を言う前に祥司は分厚い皮に覆われた先端を舌を使って刺激し始める。 音を立ててミツルの中心を飲み込みながら、同時に後ろに回した指でミツルの入口にそっと触れた。 「んっ…やめろって……そんな事したって無理だから…これ外せよ…。」 「ゴチャゴチャうるせぇな、お前は黙ってケツ突出してりゃいいんだよ。」 痺れが切れたのか、祥司は乱暴にミツルをベットに押し倒して尻を持ち上げると、犬のような格好をさせて剥き出しになった後ろの入口に指を入れる。 「んっお前……最低…。」 ミツルは誰にも見せた事の無い部分に絡みつく視線を感じて恥かしさのあまり枕に顔を伏せた。 「また泣くのか?」 「な、泣かねぇよ…。」 祥司の言葉に説得力の無い涙まじりの声で答えて仕方なく自ら尻を持ち上げた。 口は悪くても祥司の指先は震え、ミツルにも彼の緊張が伝わる。 ミツルを傷つけないように馴れない手つきで懸命に入口を広げている祥司の優しさに抵抗する力がフッと抜けていった。 「力抜けよ…。」 後ろを掻き回す指の違和感が少しづつミツルの身体を熱くさせると、同じくらいに熱くなった祥司のモノが指の変わりに入口を塞いだ。 中に入ろうとする異物から逃れるように、祥司が腰に力を入れる度ミツルの腰は前へ傾いていく。 「おい、逃げんなよ。」 「だってっ……。」 祥司は苛立ちを隠そうともせずにミツルの肩を抑えつけ、うつ伏せにさせて逃げ場を奪った。 「チッ…入んねぇな……。」 緊張で身を硬くしているからローションがヌルヌルと滑って上手く入らず、焦った祥司がミツルの上に覆い被さって中心を突き刺した。 「うぁっ……。」 背中に自分よりも昂ぶっている祥司の鼓動を感じながら、少しづつ入ってくる異物に思わず声が漏れる。 「痛いか?」 「……っ。」 祥司の問いかけに言葉が出ずに、ただ首を横に振って大丈夫だと答える。 中に入った祥司の硬さや温度に、何だか分らないが込み上げるものを感じてミツルの前も熱くなっていく。 不器用に腰を動かしている祥司の息遣いに混じって、自分でも聞いた事の無いような甘い声が漏れた。 「ぁっ……。」 ミツルの名前を叫びながら腰をぶつける祥司の動きが激しくなると、前の方に感じた熱いものが漏れてしまう感覚にミツルは小さい叫び声を上げた。 「くっ…ミツルっ…ミツルっ……。」 祥司はミツルの小さな叫び声に気付く余裕も無く、乱暴に腰をぶつけている。 ミツルの上に汗が降り注ぎ、荒い息遣いは普段の祥司からは考えられないくらい切なく擦れていた。 「ミツル……ごめん…。」 狂ったように突き上げていた祥司の腰が動きを止めると、身体を大きく震わせてミツルの中に溜まっていた欲望を吐き出して崩れ落ちた。 「おい、ミツル…。」 呼吸を整えた後、祥司は縛っていた紐を解いてうつ伏せのままのミツルの背中を抱き締めた。 「お前もイカせてやるから、こっち向けよ。」 「俺はいいってっ…。」 「何で?いいからこっち向けって。」 「いいからっ…シャワーでも浴びてろよっ…。」 「泣いてるのか…?」 焦ったように身を硬くして、頑なに姿勢を変えないミツルに祥司は今更ながら強引過ぎた行為を振り返って不安になる。 「ごめんミツル…なあ、こっち向けって。」 「な、泣いてないから……。」 心配になって無理矢理ひっくり返すとミツルの股間は濡れて、シーツはベタベタに汚れている。 「うわっ……祥司…見るなっ。」 ミツルの慌て振りに一瞬噴き出したが、一緒に感じてくれた事が嬉しくて大丈夫だよとミツルを優しく抱き締めた。 「ごめんな…シーツ汚しちゃって……。」 「いいって、身体で返して貰うから。」 照れて顔を伏せたミツルを抱き締め、大量に吐き出して汚れたモノをティッシュで拭いてやりながら祥司は嬉しそうに笑った。 「ぁっ……祥司っ…くすぐってぇから…止めろって…。」 身をよじりながら腰を引く姿に欲情して、祥司はまた元気になり始めた股間を逃げようとするミツルの腰に押し付けた。 Top |